「転職したいけど職種が決まらない」「どんな職種が自分に向いてるのかわからない」など考えている人も多いです。
職種を決められないまま、なんとなく転職してしまうと「思っていた仕事と違う」と後悔しかねません。
本記事では、転職したいのに職種を決められない人に向けて、決められない原因と希望職種の正しい見つけ方を紹介します。
最後まで読むことで、希望の職種が見つかるだけでなく、やりがい感じられる仕事を探すことも可能です!
転職では、職種を決めるのが1番大切!
転職を考えるときに大切なことは、職種を決めることです。
なぜなら、なんとなく自分にできそうかもと曖昧な判断で職種を決めてしまうと、自分の強みが活かせずにやりがいを感じられない場合があるからです。
例えば、職種を重視せずに給料や立地、企業のバリューネームだけで職種を選んでしまうと、自分の強みを活かしきれない職場環境や仕事内容の可能性もあります。

しかし、職種は約13,000種以上あるとされています。そのため、自分に合った職種選びは難しく自己分析が不足していると、職種を決められない場合も多いです。
また、自己分析は一人でおこなってしまうと、主観ばかりが先行してしまい、客観的に自分の強みや価値観を把握できません。そのため、自己分析は第三者からの客観的な視点が非常に重要と言えます。

客観的な意見はプロからのアドバイスがあると安心でき、特にキャリアコーチングサービスはおすすめです。
キャリアコーチングサービスでは、キャリアの専門家であるキャリアコーチが、面談を通してあなたの自己分析やキャリアビジョンの作成を手伝ってくれるサービスのため、第三者であるプロからの視点で職種に関するアドバイスができます。
その中でも、弊社キャリアコーチングサービス「マジキャリ」への相談がおすすめです。
なぜなら、マジキャリは転職エージェントも運営しているアクシス株式会社が提供するサービスのため、多くの職種に関する知見を持っています。

あなたの強みや価値観を分析しながら、おすすめの職種を提案したり職種決定のアドバイスをおこないます。
マジキャリでは、初回に限り無料相談を実施しています。キャリアについて悩みや不安がある場合は一度、ご相談ください。
関連記事
おすすめのキャリアコーチングサービスを知りたい人は、「キャリアコーチングおすすめ12選!転職に強いサービスの特徴や料金を徹底比較」の記事もあわせて読んでみてください。
転職で職種が決められない原因4選
転職する際には、職種が大切だと説明しました。しかし、現状は職種に悩む人が多いです。
職種を決められない原因は以下の4つが挙げられます。
原因を探ることで、自分に必要な改善策が見つけられるのです。
強みやスキルが整理されていない
転職する際に、職種を決められない原因の一つに、強みやスキルが整理されていないことが挙げられます。
なぜなら、自分の強みやスキルが整理されていないと自分がアピールできる職種が何かわからないからです。
逆に、自分のスキルや強みを理解していると、スキルや強みが活かせる職種に絞られます。さらに条件の優先順位があることで、より選択の判断はしやすくなるのです。
しかし、自分のスキルや強みはなんとなくわかる気がするけど、採用担当者に上手く伝えられない場合もあります。採用側もあなたが転職した後の働いている姿をイメージできず、不採用となる可能性も高いです。

そのため、まずは自分の強みやスキルを整理してください。具体的な方法は自己分析をおこなうことです。
自己分析をおこなうことで、過去の体験を振り返り、得意なことや大切な価値観が明確になります。
もし、自分のスキルに自信が持てないと感じる人は、ポータブルスキルを確認することをおすすめします。
ポータブルスキル
どの職種にも活かすことができる汎用性の高いスキル
例えば、コミュニケーションスキルや論理的に思考ができて問題解決ができるなどです。
転職先の職種が決められない人は、まずポータブルスキルを見直して、強みやスキルを整理してください。
関連記事
自己分析のやり方を知りたい人は「【誰でも簡単】自己分析のやり方を紹介!よくある失敗や注意点も解説」の記事を参考にしてください。
将来の理想像が明確でない
転職する際に、職種を決められない原因の一つに、将来の理想像が明確でないことが挙げられます。なぜなら、転職はゴールではなく、あなたの理想の将来を掴み取るための手段だからです。理想の将来に向けて職種を決める必要があります。
例えば、将来は起業をしたいと漠然と考えている場合、方向性は見えているけれど具体的な内容が薄いため、どの職種に転職したらいいのかわかりません。
将来は人材育成に関わる研修会社を経営して、オンライン研修をしつつ、家族との時間も増やしたいと考えると、教材をつくるパソコンスキルやコミュニケーションスキル、実績を積み上げるなどしないといけません。

上記のように理想の将来像が明確になると、スキルや実績を得るための転職をするなどの職種の選択がしやすくなるのです。
将来の理想像を明確にするには、まず「どのような生活を送りたいか」を具体的にイメージすることが大切です。仕事面やプライベートを分けて考えるのではなく、どうすれば両立できて満足感を得られるのかを整理してみてください。
関連記事
具体的な将来像が思い浮かばないときは「【年代・職種別の例文16選】キャリアプランが思いつかない原因と簡単な作り方」を参考にしてみましょう。
不安で挑戦に踏み出せない
転職する際に、職種を決められない原因の一つに、不安で挑戦に踏み出せないことが挙げられます。なぜなら、自分の強みや将来像が明確になっても、現状を変えるためには「失敗したらどうしよう」などの気持ちから転職を躊躇してしまうからです。
例えば、今よりも自分の強みが活かせる職種を見つけ出せた場合、転職するほうが将来的にはプラスになると理解していても「スキルは通用するだろうか?」「給料が下がるから生活が不安」などの理由で転職を思い悩むケースもあります。

不安を解消するためには、まずは転職理由を明確にしてください。
転職理由が明確になれば、なぜ転職をしなければいけないのかという必要性が見えてくるのです。
また、希望する職種で働いている人には話を聞くことで、自分が感じているリスクはどの程度あり得るのかも確認できます。
希望条件が現実的でない
転職する際に、職種を決められない原因の一つに、希望条件が現実的でないことが挙げられます。なぜなら、すべての希望を完全に満たす求人や企業はないからです。
前提として、企業は自社の利益や成果のために存在しています。あなたがやりたいことをすべて叶えてくれる慈善活動ではありません。
また、スキルや実績がない場合、希望している企業の選考に通らない可能性もあります。そのため、まずは希望条件を見直し、優先順位をつけてください。

優先順位をつけることで、希望する職種の選択は増えてきます。
さらに職種に求められるスキルや経験を調べることで、採用されるための経験やスキルを整理すると自分の強みやスキルに合った職種が見つけやすくなります。
希望職種を決める5つのステップ
転職するときに職種が決められない原因を理解できたと思います。では、どうやって希望職種を決めることができるのか?そのステップを解説します。
職種を決めるための具体的なステップは下記の5つです。
1.将来の理想像を明確にする
職種が決められない人は、希望する職種を探すためにも将来の理想像を明確にしてください。なぜなら、理想の未来の自分を設定することで、必要なスキルや具体的な行動方針がわかるからです。
例えば、将来は自分で有形の商品をつくって、ECサイトで販売業をする理想を描いた場合、サイト設計のスキルが必要のため、学びの時間をつくろうと考えることができます。
理想が明確になっていないと「どんな自社商品をつくるのか」「ニーズ調査は万全か」「商品を知ってもらうための発信の頻度はどのくらい必要か」などの行動計画に迷ってしまいがちです。

理想の将来像をより具体的にするためには、行動計画に優先順位をつけることをおすすめします。
優先順位をつけることで、理想の状態までの全体の流れを把握することができるからです。
また、将来の理想を思いつかない場合は、やりたくないことや苦手な環境を想像してみてください。
嫌なことは自分の価値観に合っていなかったり、他人よりも作業に時間をかけてしまうため、成果を出しづらく、やりがいも感じられないケースも多いです。

やりたくないことを思いつく限り書き出すことで、自分の得意なことやなりたい姿を見つめ直すことができます。
2.強みやスキルを整理する
職種が決められない人は、希望する職種を探すために強みやスキルを整理してください。
なぜなら、理想の将来像へ到達するためには、様々な手段の中で自分の強みやスキルから理想の姿に近づくための方法を選択できるからです。
例えば、自分の理想の将来像へ向かう方法は主に3つあります。
- 独学でスキルを学び、経験を積む
- 会社やチームに所属して、コネクションやノウハウを学ぶ
- キャリアコーチングなどを利用して方向性を定めつつ、今後のアドバイスをもらう
どの方法が最良の選択なのかは、自分の強みやスキルから考えればより早く、理想の姿に近づくことができるのです。

例えば、自分のスキルがコミュニケーションにより引き出す力であれば、会社に所属することで、上司や同僚から様々な経験を学ぶことができます。
一方、人と関わることは苦手だけど、タスクを黙々とこなせる強みを持つ人は、独学で学ぶことで自分のペースを崩さずに着実に目標へと近づくことが可能です。
自分の強みやスキルがわからない場合は、あなたのポータブルスキルを見つめ直してみてください。あなたの日常を観察することで、自分がどんなスキルや強みを持っているのか見つけやすくなります。
どうしても、一人ではスキルや強みがわからない場合は、キャリアコーチングなどのサービスに相談すると、キャリアについてトータルサポートが受けられるのでおすすめです。
3.理想実現のために必要なスキルや経験を整理する
希望する職種を見つけるためには、理想の実現のために必要なスキルや経験を整理してください。なぜなら、自分の理想の姿と現在のスキルや経験を比較することで、自分の足りないものが見えてくるからです。
例えば、将来コーチングの仕事をしたいと考えている場合、他人への悩み解決や相談の経験が足りないかもしれません。また、相手の気持ちを引き出すためのコーチングの方法も学ぶ必要があるなどスキルに関しても、自分の現在地がわかります。
スタート地点だけわかっても、ゴールを知らないと動けないですし、反対にゴール地点だけ知っていても、スタートする場所が明確でないと、いくつもの手段があり迷ってしまいます。

理想の姿であるゴール(目標)と今の現在地(持っている経験やスキル)を明確にすることで、足りないものを補う行動計画が立てられるのです。
また、スキルや経験を得るための行動計画は、ある程度の期日を決めておくことで、積極的に行動に移すことができるためおすすめです。
4.職種研究をおこなう
希望する職種を見つけるためには、職種研究をおこなう必要があります。
なぜなら、職種研究をおこなうことで、自分の興味のある職種の業務内容と得られる経験やスキルが理解でき、その後のキャリアプランが明確になってくるからです。
例えば、無形商材の営業について職種研究すると、得られるスキルや経験は以下のように考えられます。
| スキル | 経験 |
|---|---|
| ・分析力
・商品価値の説明力 ・共感力 ・本質を見抜く力 |
・不安や問題を解決した実績
・企業の売上に貢献できた成果 ・クレーム対応の経験 ・プレゼン資料の作成経験 |
将来はコンサルティングをしたい人にとって、プレゼン能力や問題解決の実績などは将来のキャリアプランを実現させるうえで、必要なスキルな経験となり得るのです。
上記のように、職種研究をおこなうことで「自分の強みを活かせる業務内容なのか」「今後のキャリアプランに役立つスキルや経験を得られるのか」などを判断できます。
しかし、企業や業界によって仕事の内容が異なるため、今後のキャリアプランにも影響を与えてしまいます。

遠回りしないためにも、異なる職種の研究においてはケースごとに分けて整理していくと最終的な職種を選ぶ時に判断しやすいです。
関連記事
キャリアプランって何?と感じた人は「最低限抑えておくべき!キャリアプランの立て方とポイントを紹介!」を参考にしてみてください。
5.強みやスキルが活かせ理想像に近づくための職種を選択する
最後に強みやスキルを活かしながら、理想像に近づくための職種を選択します。
これまでの流れにそって整理していくことで、理想の将来像とステップアップの方向性、自分の強みやスキルが活かせる職種を絞り込めている状態になっています。

最終的に残っている職種の中から、あなたの理想を実現するために、自分の強みを活かせる職種を選択してください。
絞り込んでいる職種の中には、自分のスキルが活かせない職種や環境があなたの価値観にマッチしていない職種もあるでしょう。
その場合は候補から除外し、本当に自分に向いてる職種の中から選ぶほうがリスクを回避できます。
残った候補の中で、転職する職種を決められないと悩んでいる場合は、どちらの職種が自分の将来の理想に向かって貢献してくれそうかで判断してください。

いずれも、あなたの強みや価値観とマッチしている場合は、どちらか一つに絞る必要はなく、第一候補や第二候補として、柔軟に対応していくことも大切ですよ。
また、社会の変化によっては、職種から得られるキャリアプランが大幅に変化したり、新しい職種が生まれることも考えられます。
数年後を見据えながら、業界の動向に注目しておくことも必要です。
【原因別】職種を決めるときのポイント
職種を決めるための具体的なステップがわかったところで、次は実際に職種を決めるときにつまずくポイントを紹介します。
職種を決めるときは以下のポイントを押させておくことで、つまずいた際に具体的なアプローチが可能です。
【将来の理想像が明確でない人向け】興味を行動に移す
職種を決められない原因が、将来の理想像を明確に描けない人には、興味を持っていることに対して、まずはやってみることをおすすめします。
なぜなら、最初からなりたい理想の姿が決まっている人はいないからです。多くの場合は、自分の経験や体験により、自分の価値観が形成されていく中で「将来はこうなりたい」と感じるようになります。
例えば、今まで子どものことを何とも思っていなかった人が、ボランティアを通じて子どもと関わる仕事をしたいと感じるようになるかもしれません。
実際に保育士に転職し、やりがいを持ったことで「天職だ」と感じるようになるケースもあるのです。

一方で、やりたくないことについても思案することは大切です。
やりたくないことや苦手なことが理解できていると、将来こうなったら嫌だと感じることを回避できます。
リスクを回避するためにどの行動を選択すべきかも見えてくるため、逆の発想も大切にしてみてください。
【強みやスキルが整理されていない人向け】強み発見ツールや他己分析を活用する
職種を決められない原因が、強みやスキルが整理されていない人の場合は、強み発見ツールや他己分析を活用してみてください。
なぜなら、あなたの強みとは他の人と比べて、意識していなくても自然と成果に繋がる行動ができるため一人で見つけるのが難しいからです。

そのため、他人からの視点で役立っていることを教えてもらったり、強み分析ツールを使うことで客観的な意見が得られます。
例えば、身近で誠実な人に、自分の素敵なところと直して欲しいところを尋ねてみてください。できれば一人ではなく、数名に確認を取るといいでしょう。
その際、いきなり聞くのではなく、きちんと経緯を話すことで相手も納得して答えてくれる可能性が高いです。
また、強み発見ツールも強みや人間性、適職などを統計的なデータから導き出せます。無料のツールを多く、一度使ってみると良いかもしれません。

他己分析や強み発見ツールのデメリットとして、間違っている判断や診断をされるかもしれないという点があります。
他人からは、あなたの行動は見えますが、思考まではわかりません。強み発見ツールでは、統計的なデータであるために、データを分類した中から導き出した内容と言えます。
あくまでも参考意見として捉えておきましょう。
【不安で挑戦に踏み出せない人向け】転職の目的を明確にする
職種を決められない原因が、失敗などが不安で挑戦へと踏み出せない場合の人は、転職の目的を明確化してみてください。
なぜなら、リスクを考えすぎることで、転職時期を逃してしまう可能性があるからです。
例えば、転職の目的が明確でないと「この企業は仕事内容が大変そう」「自分にできるか不安」などの失敗を恐れる理由から転職することを無意識に先延ばしにしてしまいます。
先延ばしにしてしまうと、求人情報を見なくなったり、転職へのモチベーションが低下するなどもあり得るのです。

特に未経験職種への転職では、どうしても仕事内容を覚えることが多く、慣れるまでには時間が必要です。
できるできないで判断するのではなく、「強みを活かせてやりがいを感じられるのか?」「将来の目標に向かってステップアップできるのか?」という転職の目的を見直してみてください。
また、本当に転職すべきか悩んでいる場合は、期日を決めて目標達成までの道のりを逆算すると、今すぐに転職すべきか判断しやすくなります。
【希望条件が現実的ではない人向け】希望条件の優先順位をつける
職種を決められない原因が、希望条件が現実的でない場合は、条件に優先順位をつけてください。
なぜなら、すべての希望条件を満たす求人を見つけることは難しいからです。そのため、希望条件の中で優先順位をつけることで、これだけは譲れない条件を明確にできます。
例えば、希望条件が以下の内容だった場合、優先順位をつけることで代替案などを考えられます。
希望条件の例
- リモートワーク
- 現職よりも給料が高い
- 週休3日
- 福利厚生が充実
上記の条件に当てはまる求人は、なかなか見つからないです。そこで、優先順位をつけていきます。
優先順位は、自分が譲れないと考えている価値観を深堀りすることで見えてきますよ。
ここでの優先順位は、自分の時間を大切にしてプライベートを有意義にしたい場合です。
希望条件(優先順位あり)
- リモートワーク
- 残業が少ない
- 週休2日でも可、ただし土日祝休み
- 給料は高い方が良いが現状維持でも可能
- 福利厚生は必要最低限あれば良い
自分の時間を大切にするためには、リモートワークで残業が少ない企業という条件を満たせば満足できる可能性が高まります。

希望条件をすべて満たそうとせずに、どうすれば満足できるのかを考えることが大切です。
上記の場合は「リモートワーク」「残業が少ない」の2点が必須条件です。また、休みの日数や給与などに関しては、あれば望ましいという条件付けをしているのです。
このように優先度の高いものと低いもので分けて考えると優先順位を整理できます。
最も重要なことは、希望条件の基盤である自分の価値観と、将来の理想の姿に向かうためのキャリアプランがマッチしている職種を選ぶことが大切です。
転職で職種が決められなかった人の体験談
ここでは、転職したいと感じているのに、職種が決められなかった人の体験談を紹介します。
以下の体験談では、収入に不安を抱えていたり、自分が何をやりたいのかわからなくて、職種を決められなかった人のリアルな解決方法が書かれています。
あなたも職種を決めるための判断材料として、参考にしてみてください。
不安で挑戦に踏み出せなかった人の体験談
不安で挑戦に踏み出せなかった人の体験談
不安定な収入で生きるのは難しいと思い、どう進むべきか悩んでいた時、インターネットで自分の働き方を相談できる場所を見つけ、そこでマジキャリに出会いました。
コースの前半では、「現状把握」「過去を振り返る」「仕事の棚卸し」といったワークを通して、自己分析をしました。コーチと一緒に自己分析をすることで、実はITエンジニアにも向いていることがわかりました。なぜなら、面談で「指針があるときは他者より圧倒的に秀でることができる」という強みを見つけたからです。自分の強みを広く見ることで、適職の選択肢が広がりました。
後半では、自己分析を基に、将来の自分の目標や具体的な仕事、必要な行動について考えました。
①ITエンジニアとして本業に取り組み、実績を積み上げる。
②結果を出すまでに蓄積された知識をブログやSNSで発信する。
③ブログやSNSで稼げるようになったら、そちらにシフトする。
最終的に、親からも認められ、スキルアップもでき、自分らしく働ける理想の働き方をデザインすることができました。
出典:note
関連記事
マジキャリの利用を検討している人は、無料面談の流れや料金について詳しく解説している「マジキャリは無料相談だけでも大歓迎!利用するメリットも徹底解説」や「マジキャリの料金は高い?他のキャリアコーチングとの相場を徹底比較!」の記事も読んでみてください。
将来の理想像が明確でない人の体験談
将来の理想像が明確でない人の体験談
転職活動のやり方が全くわからず、自己PRも全く書けず、自分が何をしたいのかもわからない…と途方に暮れていた矢先、SNSの広告でマジキャリを見つけました。
マジキャリでは以下のような内容をおこないました。
①現状把握
➡自分分身に「なぜそう思うのか?」と問うことは想像以上に大変でしたが、思いつくものを挙げていくうちに「今より良くするにはどうしたらいいか」が見えてくる感覚がありました。
②過去の振り返り
➡自分の強み、弱み、苦痛に感じること、やりがい、考え方の癖を見つけることができました。幼少期から振り返ったことで、自分の本心を確認できた気がします。
③仕事の棚卸し
➡現職では「ミスなくお客様に商品を納品すること」が日々の目標であり「トラブルなく1日を終えること」がやりがいだと思っていましたが、これは「人に迷惑をかけたくない」というのが動機でhave toが強いのかもしれないと気づきました。
④将来設計
➡この2点を意識したところ、それまで全く書けなかった5年後のありたい姿が浮かび上がってきました。小学生の頃から将来の夢の作文が苦手で、いつも周りに合わせてそれっぽいものを書いていた自分が、自分の中から将来ありたい姿を見つけることができるなんて驚きでした。
⑤今後のプランニング
➡小さなことでもいいので、とにかく具体的にすることが大切だと感じました。そのためには情報収集も必要だと感じています。
このワークをおこなったことで、自分自身のやりたいことが明確になってきました。
今後は、現職を続けながらカウンセリングの勉強を進めていきたいと思います。直近の自分の経験も踏まえてキャリア支援ができるカウンセラーを目指したいと思ったので、キャリアコンサルタントの資格取得を第一目標として勉強していきたいです。
出典:note
職種を決定するときの注意点3選
以下では、職種を決定するときの注意点を3つ紹介します。注意点を知っておくことで転職後のミスマッチを避けることができるため、非常に大切です。
しっかりと理解してリスクを避けながら、職種を選んでください。
十分に職種研究をしていない
職種を決定するときのポイントの一つは、十分な職種研究をおこなうことです。なぜなら、未経験の職種に転職する場合、職種研究をしていないとミスマッチが起こりやすいからです。
転職先でミスマッチが起きてしまうと「イメージとは違った」「もっと別のところで働きたい」と考えてしまうケースもあり、早期離職をしてしまうと次の選考では「すぐに辞めてしまいそう」という理由で選考対象外となる場合もあり得ます。
ミスマッチを起こさないために職種研究は大切です。職種研究の具体的な方法は以下の表にまとめています。
| 調査内容 | 調査方法 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・企業の公式ホームページ
・ホームページで調査 |
| 一日の流れ | ・インタビュー記事
・YouTube |
| 平均残業時間 | ・「職種 残業時間」で検索 |
| 平均年収 | ・ホームページで調査 |
| やりがい | ・noteの記事
・インタビュー記事 |
| 求められるスキルや経験 | ・ホームページ
・SNS |
| よくある悩み | ・Yahoo知恵袋
・希望の職種に従事している人のブログ |
| 転職後のキャリアプラン | ・インタビュー記事
・自己分析 |
主な調査方法やインターネットやYouTube、SNSなどから希望している職種の調査が可能です。また、活字に苦手意識がない人は、職種に関する本から調べることで職種の全体像が見えてきますよ。
しっかりと調査し、職種研究をおこなうことでミスマッチを減らすことが大切です。
強みが活かせない職種を選ぶ
職種を決定するときのポイントの一つは、自分の強みを活かせる職種を選ぶことです。
なぜなら、強みを活かせる職種に転職することで、得意なステージで仕事ができるため、他人よりも成果が出しやすく、評価される機会が増えるからです。
企業から評価されるとキャリアの可能性が広がります。
- 給与が上がる
- 周囲から頼られる
- 出世の候補に挙がる
- 実績がつく
- やりがいを感じられる
上記のようにキャリアの積み上がっていくのです。
一方「やりたいことや好きなことを仕事にしてはいけないの?」と感じる人もいるでしょう。

結論から伝えると、好きや憧れから職種を選ぶことはおすすめしません。
なぜなら憧れが強い分、理想と現実のギャップを感じやすいからです。
例えば、テーマパークで仕事したい人は、8時に出勤し22時に退社するなど勤務時間が長かったり、平日は事務作業をすることも多く、憧れとは違った場面に直面するケースも多いです。
理想と現実のギャップやミスマッチに悩まされないためにも、強みを活かせる職種を選択してください。
職種決定の理由と原体験がつながっていないこと
職種を決定するときのポイントの一つは、職種決定の理由と原体験が繋がっていることです。
なぜなら、職種決定の理由と原体験が繋がっていれば、転職先で仕事をする際に大きな原動力となるからです。
例えば、大手企業の安定性やベンチャー企業の将来性などから職種を選択してしまうケースがあります。
しかし、実際の体験から感じた強い動機や自分の強みに職種がマッチしていないと、ネームバリューで仕事をすることになり、結果成果を出せずにやりがいを感じられない場合があるのです。

原体験に基づいたあなたの価値観や強みがあれば、職種選びの際に興味を惹かれます。
「なぜ、この職種に興味を持ったのだろう」と考えてみることで、自分の経験や価値観を紐づけてみてください。
価値観や強みが興味のある職種にマッチした場合は、原体験をもとに採用担当者に自分の強みを伝えることで、採用側も納得できる受け答えをすることができます。
補足ですが、知名度や将来性を職種決定の理由の一つとすることは問題ありません。

ですが、最も大切なことは自分の強みを発揮できる職種を選ぶことです。
後悔しないためにも、知名度や将来性だけで職種を決定することは避ける方が無難と言えます。
希望職種が決められない人は、マジキャリ!
「どんな職種がいいのかわからない」「求人情報だけでは判断できない」そう感じた人もいるでしょう。

あなたに合った職種を見つけて選ぶ際は、十分な自己分析と将来どうなりたいかという理想像の設定が欠かせません。
しかし、自分の理想像の設定や自己分析は、そもそも一人でおこなうには難易度が高いのです。なぜなら、強みや価値観、経験とスキルの棚卸しは客観的な視点から判断する必要があるからです。
一人で強みやスキルを分析しても、表面的なものや「きっとスキルがあるだろう」と憶測で間違った自己分析をしてしまいます。
また、将来の理想の姿といえど、現実味がなく実現不可能な設定では、努力の方向性が見えにくいことから、客観的な視点からのアドバイスは必要です。

マジキャリでは、転職エージェント事業も運営しているアクシス株式会社が提供するキャリアコーチングサービスのため、転職市場に詳しく、職種に関しても知見も幅広いです。
マジキャリに相談することで、将来のなりたい姿を実現可能な設定にブラッシュアップすることができます。
また、マジキャリの最大の強みでもある徹底的な自己分析から、あなたの強みや価値観を深堀りし言語化するためのお手伝いができるため、自分に向いてる職種を選択することが可能です。
今ならマジキャリは初回に限り無料相談をおこなっています。

お気軽に相談できますので、職種を決められない人や、キャリアの悩みがある人はお問い合わせください。
関連記事
キャリアコーチングについてもっと知りたい人は「キャリアコーチング12社の口コミを徹底解説!結局どこが1番いいの?」を参考にしてみてください。
転職したいが職種を決められない人によくある質問
最後に転職したいけど、職種を決められない人が感じるよくある質問にお答えします。
いずれも転職活動をするときに不安に感じる内容です。あなたにも当てはまる場合は参考にして上手な転職活動をしてください。
未経験転職は難しいですか?
結論から伝えると、未経験転職は年齢によって難易度が変わります。
| 年齢 | 転職難易度 | 採用基準 |
|---|---|---|
| 20代 | ◎ | 十分なスキルがなくてもポテンシャルで採用される可能性が高い |
| 30代 | ◯ | スキルや経験が必要になる。企業が求める適性やスキルがあれば採用される可能性は高まる |
| 40代 | ✕ | 成果を出した実績が必須条件。人材育成やマネジメントを任せられる人物で判断されるため、転職を難しい |
上表のように、20代では、スキルがなくてもポテンシャルから転職可能です。
また30代では、これまでの実績が評価されます。一定のスキルや経験を評価されるため、難易度は上がりますが、転職の可能性があります。

しかし、40代になると人材育成や企業のマネジメントを任せられる人材が求められるため、成果の実績は必須です。
そのため、40代からの転職は非常に難しいと言えます。
未経験職種へ転職する場合は、自分のスキルを見直してください。専門的なスキルも大切ですが、ここで重視するのはポータブルスキルです。
ポータブルスキル
どの職種にも活かすことができる汎用性の高いスキル
例えば、コミュニケーションスキルや交渉力の高い人は未経験でも営業職へ転職しやすい傾向があります。
また、未経験転職だとしても、計画性を持ってスキルアップすることで採用の可能性を高めることが可能です。

例えば、個人を対象とした保険営業マンが将来コンサルティングファームへ転職を希望している際、まず法人営業へ転職することで、企業の悩みを解決する力がつきます。
問題解決スキルや提案力、営業の実績を伝えることで未経験でも、コンサルティングの職種に就ける可能性が高まります。
未経験職種への転職をしたい場合は一度、自分のスキルやロードマップを整理することが大切です。
転職で何がしたいかわからない20代はどうすればいいですか?
転職で何がしたいのかわからない20代の人は、強みを活かせる職種を選ぶことがおすすめです。
なぜなら、強みを活かせる仕事に就くことで、仕事にやりがいを持てたり、企業に貢献することができるからです。
例えば、マルチタスクをこなすことが強みの人は、事務職やコンサルティング、マーケッターなど様々な作業を計画を立てて同時に進行できる職種に強みを発揮できるのです。
現代は、YouTubeやSNSの発信から、さまざまな働き方や人生の過ごし方が紹介されているため、今の会社にやりがいを持てない人ほど「もっと自分に向いてる仕事がしたい」と感じる社会になりました。

誰でも憧れが持てる夢のある社会と言えば聞こえはいいですが、自分の強みがわからないままで転職してしまうと、憧れる気持ちが高まっているため「こんなはずではなかった」と感じてしまう人も多いです。
自分の選択を後悔しないためにも、あなたの強みが活かせる職種に転職することが大切です。そのためには自己分析が必須となります。
自己分析をおこなえば、あなたの体験からスキルや経験、実績などを徹底的に棚卸しするだけでなく、棚卸しした内容から、自分の強みを言語化していくのです。

自分の言葉であなたの強みを伝えることができれば、採用担当者もあなたが働いているイメージが湧きやすく、選考にもプラスに働きます。
自分独自の強みを知っていれば、あなたが得意とする環境で勝負できるため、成果も出しやすく、結果的に仕事にやりがいを持つことに繋がるのです。
どうしても一つに決められない時はどうすればいいですか?
どうしても職種を一つに決められない人は、期日を決めることをおすすめします。
なぜなら、期日を決めなければ、いつまでも希望条件に完全に合う職種を探したり、ダラダラと情報収集ばかりしてしまう可能性があるからです。
例えば、試験勉強を一夜漬けでおこなうときの「わからない範囲は捨てて、理解できる場所に絞って覚えよう」としていることに似ています。

普段は職種に悩んでいても、期日が迫ると人は選択ができるのです。
また、どの職種に転職してもリスクはあります。どんなに職種研究や情報収集をしても、実際に仕事をしてみないことには、どんな職場環境なのかはわかりません。
そのため、期日を決めてしまうことで、その後の時間を選考対策や適性検査の対策に時間を使うことができます。

期日を決めても先延ばしてしまいそうな場合、期日を決めた後のスケジュールも同時に決めておくと、行動すべきことも明確になり迷うことなくスムーズに転職活動しやすくなりますよ。

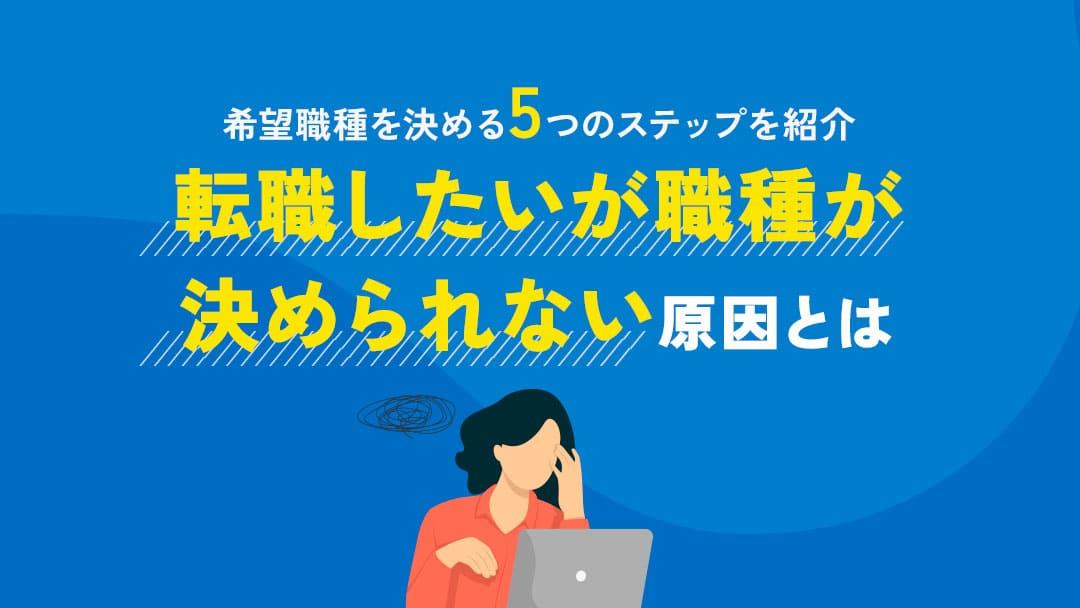




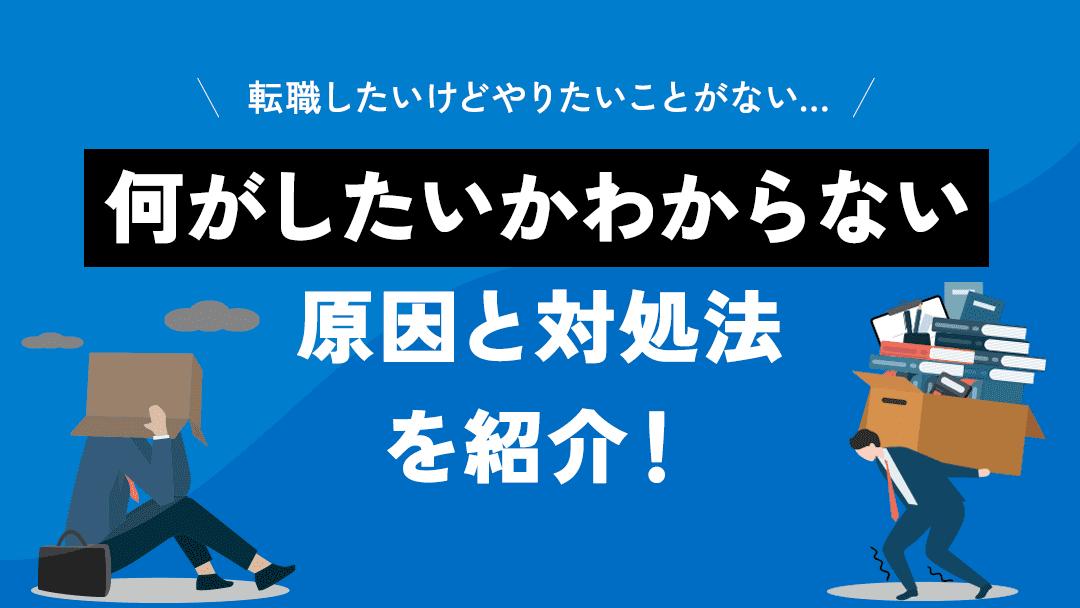
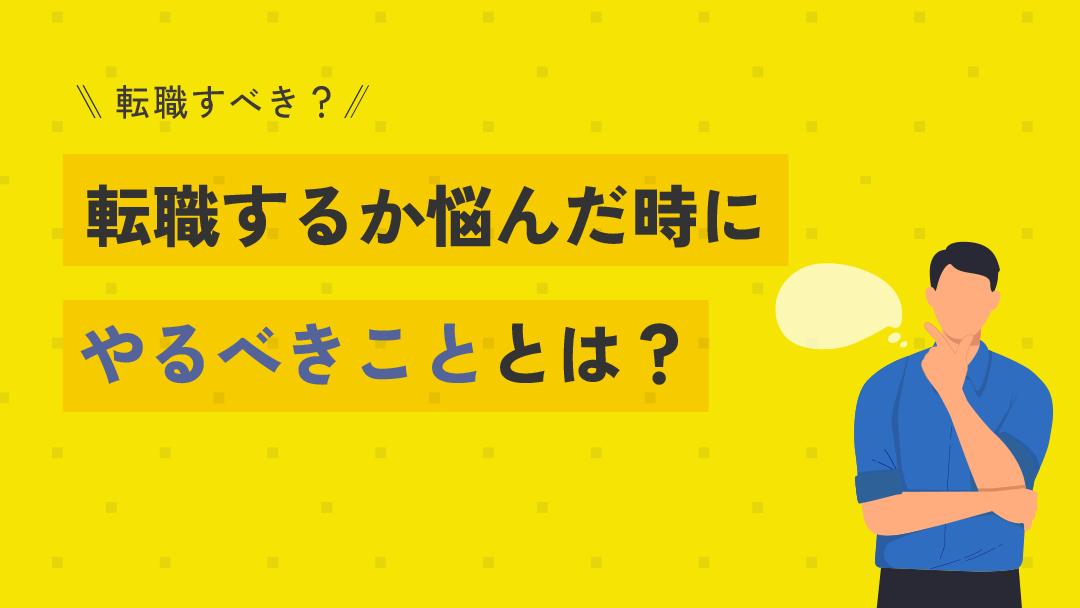





あなたに合った職種を選ぶことで、自分の得意なことを会社で活かすことができ、やりがいを感じながら仕事に取り組めるのです。